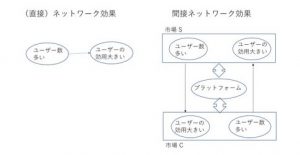感染症の大流行が時代を画す:After Corona (AC) の世界
ペストの流行が中世から近代への移行を促進したことや、天然痘がアステカとインカ両帝国の滅亡に深く関係していたことは、史実として認められていると思います。COVID-19も、現代を次世代へと変化させる原動力となるのでしょうか? 既に世間では、after-Coronaとかwith-Coronaという語が飛び交っていますが、これからの世界がパラダイム・シフトを起こすとすればどのような点か、変化の方向性だけは(情報法の将来像を描くためにも)書き留めておきましょう。
・大きな3つの変化が不可避
この問題については、多くの識者が既に見解を表明しており、一見私が付け加える余地がなさそうですが、実は大きな欠落があるようにも思えます。というのも、COVID-19は次の3つの大変化を伴うはずだと思うからです。① 目的意識を持って実行すべき目標としての「世界人口の抑制」、② まやかしではない真の「働き方改革」、③ “Small is beautiful.” に近い「新生活」(新常態あるいはnew normal)の3つです。
①Social Distanceから世界人口の抑制へ
感染を減らすには接触機会を減らすのが早道なので、social distanceが重要だと言われます。しかし距離感が重要なのは、(a) ヒトとヒト以外の生物の間、(b) ヒト相互の間、(c) 裕福なヒトとそうでないヒトの間、の3つに分けて考えなければなりません。(b) が一般的なsocial distanceですが、(c) はやや違った趣があります。シンガポールで外国人労働者の宿舎で2次感染が大量発生したことや、ブラジルやインドのスラム街(ファベーラ、ダラビ)で感染が広まったらどうなるかを考えれば、感染症対策と同時に差別を助長しない特段の配慮が必要でしょう。この場合distanceは「必要悪」ではなくdivideに近い「克服すべき課題」です。
そして、最も軽視されているが最も重要なのは、(a) のヒトとヒト以外の生物の間の距離の取り方、より直截に言えば、「ヒトは他の生物の縄張りを侵すな」ということでしょう。他人事のように思われるかもしれませんが、わが国でもクマやサル、イノシシなどが住宅地に出没している状況は、「食べ物が不作だったから」で片づけることはできず、「ヒトが増えすぎて生物の縄張りを侵したから」ではないかと、疑ってみる価値がありそうです。
この現象をよりマクロの視点で捉えれば、「宇宙船地球号に乗船できるヒトは、最大何億人か」という問題提起とみなければなりません。世界人口は既に70億人に達し、2050年には90億人を超えると予測されています。「それだけの人口を支える食料やエネルギーがあるのか」と問うヒトはいましたが(有名な「成長の限界説」)、「それだけヒトが増えれば他の生物との間に生存競争が始まる」という懸念を表明するヒトは少なかったと思われます。COVID-19から教訓を得るとすれば、「ヒトは他のヒトと交流しなければ生きられない」と同時に、「ヒトと他の生物との共存には限界がある」という事実ではないでしょうか。
とすれば、国際社会は人口の抑制に真剣に取り組まねばなりませんが、これには革命的な発想転換が必要かと思います。例えば、産児制限を宗教的に拒否するヒトがいますが、そのような発想には「第2次宗教改革」が要りそうです。また、小さな子供を労働力と捉える見方に対しては、倫理観に訴えるだけではなく、経済的にも自立できるだけのエコ・システムを考えねばなりません。しかも、人口減少は緩やかにしか効きませんから、長期計画として取り組む必要があります。
今回のパンデミックを「奢りすぎたヒトへの警告」と見る向きがあります。教訓と受け止めて自ら改革するなら良いのですが、「結局は天罰として何千万人もの犠牲者を出さねば収まらない」と諦めるのであれば、危険な発想のように思われます。私もそんなに楽観的ではありませんが、少なくとも「ヒトの意思で人口を抑制する」という目的意識を持って実行することができなければ、私たちは「霊長類のリーダー」を誇れないでしょう。
②真の「働き方」改革:個人と組織の Distance
Social Distanceの次は、個人と組織の適度の距離感が問題になります。少なくともわが国では、両者の関係が「支配―隷属関係」と言われたり、隷属する側が「社畜」と呼ばれたりしているので、両者間の適切な関係の再構築が不可欠です。現在わが国では「働き方改革」が叫ばれ、今回の騒動を機にテレワークなどが普及しそうですが、企業と個人の間のarm’slength relationship(「つかず離れず」の関係)が保たれなければ、「絵に描いた餅」か「仏作って魂入れず」に終わるような気がします。直近の黒川検事長事件は、検察と権力、検察とメディアの間の距離の取り方を誤った、典型的な事例かと思います。
また「働き方改革」の一環として、週休3日制などが論じられていますが、そもそも「皆が同じ時間に同じ場所で働く」というのは工業社会の特徴で、情報社会には不適ではないでしょうか。市役所や教会・大学などの立派な建物には時計がついていることが多いのですが、それこそ「時間は誰にも共通」「時間に合わせて行動しましょう」という倫理観を、象徴しているように思われます。
そして、マックス・ウェーバー流に言えば「プロテスタンティズムの倫理」が資本主義の精神と調和的であったように、「時間に合わせて行動する」ことが、わが国の精神風土と極めて調和的であり、戦後の驚異的経済発展を支えてきたことを忘れてはなりません。しかも、わが国の教育制度が、そうした「時間に合わせて行動する」規律を広め、均質な労働力を供給する意味で、多大な効果を発揮してきたことも。
とすれば、コロナ以前に議論されていた「働き方改革」は、依然として工業社会の延長線上での「働き方」をモデルにしており、コロナ以後はそれを根本から覆すような「真の」改革が求められている、と思われます。しかもAI(Artificial Intelligence)が予測を上回る速度で発展していることから、「AIとの付き合い方」の面から「ヒトが何日働き、後は機械に任せれば、経済は維持できるのか」といった、先輩世代が経験したことのない課題を解かねばなりません。
しかし思わぬ展開もありました。例えば前述のテレワークも、「通勤電車の密を避けるため」という受け身の姿勢で始まったものが、案外旨くいっているようです。その過程で、これまでLife-Work Balanceが著しくWorkに偏っていたことが自覚されつつあります。若い世代が、私のように「24時間戦えますか?」という強迫観念に囚われることなく、自律的に労働の内容と時間を選ぶことができれば、コロナ禍を福に転ずることができるかもしれません。
③21世紀の新生活運動としての Small is beautiful.
そして最後は、生活に関する新常識(あるいは新常態)です。ここでは、「淳風美俗」とは言えない「弊風醜俗」を捨てることから始めましょう。1955年に当時の鳩山首相が提唱した「新生活運動」は、高度成長期に勢いを失いましたが、現代版としての復活です。
例えば「3密(密閉・密集・密接)を避ける」というのは、感染症対策から生まれた教訓ですが、そのままAfter Coronaの生活指針にもなり得ます。イタリアほどではないにしても、わが国も人的交流を大事にし、同調圧力が強いからです。この連載の第46回で紹介した、わが恩人の1人である庄司薫さんが、薫シリーズの中で繰り返し「どっと繰り出す」日本人の習性を描いています。この現象は、自粛が要請されていた時期に海辺や観光地に出かけた外出好きによって、繰り返されています。
同じように、接待・贈答文化は美風とも言えますが、30年余にわたるサラリーマン生活では、そのマイナス面も体験済みです。百貨店はここぞとばかりに「おすすめ品」を勧めるせいか、受け取る側には同じものが「どっと」届きます。日持ちしないものも多く、どなたかに差し上げてもご迷惑かと悩んだものです。その後、不用品を買い取る者が現れ、遂にはカタログ方式も登場しましたが、豊かになった現代では「頂いて嬉しかった物」は絶滅危惧種ではないでしょうか。接待はやめて自分で払い、物は自分で買いましょう。
そして、コロナ対策の最大の成果は、ステイ・ホームです。自粛期間中に、多くの人が一時的にせよ、カイシャ人間から家庭人になりました。「24時間戦う」ことをやめて自分の生活ペースを取り戻し、家族を大事にしました。私事ですが、長男が育児休職を取り、当時は珍しかったのでテレビのインタビューを受けた際「どうしてイクメンに?」と問われ、彼が「自分が子供の時、父親が家にいなかったから」と答えたのを見て、私も宗旨替えしました。後悔先に立たず、ですが。
しかし、ステイ・ホームの要請の中で「自粛疲れ」が問題になった原因の1つが、わが国の住環境にあることは見過ごせません。かつて「ウサギ小屋」と揶揄された狭小住宅からの脱却がなければ、ステイ・ホームは軟禁に近くなり、疲れるのは当たり前です。3年余米国暮らしをした私からすれば、バスルームが2室以上あれば、仮にパートナーが新型コロナに罹ったとしても、感染を防ぐことはさほど難しくないと思われます。すぐにそこまで実現することは困難ですが、人口減少を利用して、かつての団地の2戸を1戸にするなど、改善の余地はあるでしょう。
こうした変化は、自然に継続することが期待されますが、運動論的な展開も必要かもしれません。その際、画一的な運動ではなく、多様な展開を許容することが不可欠です。それには「新生活運動」が古すぎるとすれば、“Small is beautiful.” を思い出すのは、いかがでしょう。イギリスの経済学者シューマッハーによって1973年に出版された書籍は、石油危機を予言した書としてベスト・セラーになりました。
しかし、実は有名になったタイトルの標語は本文中に一度しか登場せず、強調されていたのはappropriate technologyの方でした。つまり、先進国はとかく最先端技術途上国に移転したがるが、それが相手国にとって最適解とは限らず、それぞれの国や地域の事情に応じた「適正技術」があるはずだ、というのです。これは途上国に当てはまるだけでなく、「リニアは本当に必要か」という問いとして、私たちにも関わってきます。
・若い世代の「適正」な選択に期待
このように、COVID-19を機に、既に世界の各所で多様な変化が生じています。若い世代が、多くの選択肢の中から「適正」なものを選択することに、期待したいと思います。